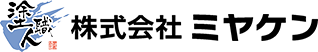外壁のサビを塗装する方法は?発生原因と補修手順を画像付きで徹底解説!
2023.01.04更新 外壁塗装

新築してから10年以上経過したお家で、外壁のサビでお悩みの方はいらっしゃいませんか?初めはあまり目立たなかったサビを放置すると、もらいサビやサビ汁の原因になり、見た目も悪く補修も大変になってしまいます。
ご自身でサビ落としをしたり、サビの上から塗装をすると、一時的にはキレイになりますが、長持ちしないケースも多いようです。
外壁塗装専門店のミヤケンでは、これまでたくさんのサビでお悩みの方のご相談に対応してきました。今回の記事では、サビの種類や塗装方法、メンテナンスでの注意点など詳しくご紹介。
金属サイディングのガルバリウム鋼板はサビやすいのか、サビが発生しやすい素材も詳しく解説します。
目次
外壁にサビができる原因

前回の塗装からおおよそ10年経過すると、外壁は劣化が進み、サビやひび割れなどの初期症状があらわれます。
外壁にサビができるのには、このような原因が考えられます。
外壁の防水性低下
一般的に金属や鉄に発生するサビの原因は、水の影響が考えられるでしょう。塗装したばかりの外壁は、塗料の防水効果によってサビが発生しにくい状態を保っています。
しかし時間の経過とともに、防水効果は弱まり、雨が外壁に溜まりやすい状態になるため、鉄部が水の影響を受け、サビが発生しやすくなります。
手抜き工事
外壁塗装は、3度塗りで仕上げるのが一般的です。塗料メーカーの仕様書にも、3度塗りを指定しているので、1度塗りや2度塗りで仕上げている業者は、規定を満たしていない工事の可能性があります。
このほかにも、下地処理が十分でない、防サビ材を塗布していないなどの手抜き工事があるかもしれません。
これらは、故意に作業を省いた可能性もありますが、職人の経験不足が招く施工不良も考えられるので、業者選びは慎重におこないましょう。
もらいサビ

もらいサビといって、お家と関係ないところで発生したサビが、雨や風の影響で、外壁に移ってしまうことがあります。
例えば、外壁に寄りかけていた自転車やスコップなどに発生したサビが、外壁のほうにまで流れて付着するのがもらいサビです。もらいサビは、金属製の外壁だけでなく、窯業系サイディング外壁やモルタル外壁など、金属以外の外壁にも発生するのでご注意ください。
今すぐにできる予防策として、もらいサビしやすいものを、外壁の近くに置かないことです。
- 自転車
- 照明
- フットライト
- 脚立
- ホース
- スコップ
このようなものを外壁の近くに置いておくと、サビが外壁に移ってしまうので、できるだけ離しておきましょう。
さらにに詳しく外壁にサビができる理由を知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。
外壁にできるサビの種類

外壁のサビは、場所や発生時期によって原因や特徴が異なります。サビを放置すると、建物の内側にまで浸食し、住宅の耐久性・耐震性が低下する原因になりかねないので、早めに対処しなければいけません。
外壁でアルミや鉄、ステンレス、ガルバリウム鋼板を使用している金属系サイディングにはサビが発生しやすいとされています。
鉄を使用した金属系の屋根材も、サビが発生しやすくなるので注意が必要です。
この機会に、お家の外壁や屋根のサビはどのようなものかご確認ください。
赤サビ

外壁や屋根の表面の、鉄や銅の素材によく見られるのが赤サビです。赤みがかかっていて、一度できたサビは、そこから一気に進行しやすいという特徴があります。
赤サビは、空気中に含まれる酸素が影響し、鉄の表面に酸化水酸化鉄が形成されることが原因で発生します。外壁や屋根のほかにも、雨樋を支えている金具や柱に見られることもあり、赤サビが進行すると、鉄や銅がもろくなるため注意が必要です。
さらに、潮風の影響を受けやすい海沿いにお住まいの方は、赤サビが発生しやすいので、半年に1回程度の水洗いを心がけましょう。
赤サビが発生していても、進行していなければ、サビ専用の洗剤やブラシなどで落とせる可能性があります。定期的な水洗いなどのメンテナンスをおこない、症状が進まないうちに対処しましょう。
サビはこのほかにも、何種類かに分類されるので、こちらの記事でもご確認ください。
サビ汁

サビ汁は、コンクリート中の鋼材や仮設材が腐食して、茶色や褐色の腐食生成物が表面にしみ出したものです。
サビ汁の発生した外壁の補修では、部材の耐久性に影響を及ぼす鋼材の腐食が進むのを停止させる工法が一般的。仮設材の補修では、腐食が進行している鋼材は除去する必要があり、専門的な技術を要するので、業者に依頼した方がいいでしょう。
サビ汁は、見た目も悪く、劣化が進むため、早めの対処を心がけてください。
外壁塗装部にできたサビの落とし方

ここからは、外壁や屋根にできてしまったサビの落とし方を解説します。サビの進行度合いや発生箇所によってやり方が違ってくるので、正しいやり方と用具でサビとりをおこないましょう。
自分で落とせる外壁や屋根のサビは、もらいサビなどの小さなもの、もしくは発生したばかりの表面的なサビです。大きさや程度の判断は難しいですが、紙やすり・布やすりで削り落とすことができる程度のサビであれば、自分で落とせる可能性があります。
ただ、やすりをした部分は、素材がむき出しになっているため、そのままの状態ではいずれまたサビが発生する原因になりかねません。少しでもサビが残ると、そこからサビが広がり劣化するので、削り残しがないか確認しながら丁寧におこないましょう。
では、サビの落とし方を詳しくご紹介します。
軽度のサビの場合

このようなサビはご自身で落とすことができるのでお試しください。
- 小さなサビ
- 表面的なサビ
- 低い場所のサビ
ここからは、簡単にできるサビの落とし方をご紹介します。
1 壁をキレイに洗浄
初めに、サビが発生した外壁全体を、家庭用ホースで洗浄して、表面のサビを落とします。
このとき、ホースの先を指で潰して、勢いよく水を掛けることがポイントです。高圧洗浄機などがある場合はご使用ください
2 サビ用洗剤とブラシで洗浄
ホームセンターで販売されているサビ取り用洗剤を使用すると、水洗いで落ちなかったサビが落ちやすくなります。
変色防止のためにも、最後によく洗剤を洗い流してください。
<ブラシ・スポンジの使い方>
ブラシやスポンジなどを使用する際には、外壁を傷つけないように、やわらかい素材のものを選び、丁寧に洗い落とすことがポイントです。
もらいサビや軽度のサビは、水洗いしただけでもキレイになりますが、外壁内部に浸入したサビはこれだけでは落としきれないので、根本的な解決にはなりません。まずは、専門業者にサビの状況を確認してもらい、対処や補修のアドバイスをもらいましょう。
高所や広範囲のサビの場合

激しい劣化をともなうような大きなサビ、高所部分のサビは、ご自身では手をつけず、すべて業者に依頼して対処してもらいましょう。
症状が進行しているサビは、外壁材や屋根材も腐食している可能性が高いので、安易にやすりがけをすると状態が悪化します。
屋根や雨樋などの高所では、素材の腐食で脆くなった足場が倒壊し、事故を招く危険があるので、安全面を考慮し自分で作業するのはやめておくべきでしょう。
外壁のサビの落とし方や補修方法は、こちらの記事もご確認ください。
関連記事:外壁のサビ発生の対処法2
サビの上から塗装する方法
引用元:アサヒペン公式
サビが発生した際の外壁は、サビを完全に落としてから塗装を施すのが一般的です。しかし、サビの上からでもそのまま使用できる塗料があるのでご紹介します。
家庭用塗料専門メーカーのアサヒペンから販売されている、水性高耐久鉄部用です。
【水性高耐久鉄部用】
<特徴>
- 水性で塗りやすい低臭タイプの鉄部用塗料
- 特殊強力サビドメ剤の効果でサビの上から直接塗れます(ポロポロと取れるようなサビは取り除く必要があります)
- 特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム、紫外線劣化防止剤の相乗効果により耐候性に優れています
- 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスにも塗装できます
<適した場所>
- 扉
- フェンス
- シャッター
- パイプ
- 機械器具
- 農機具など屋内外の鉄部・鉄製品
- ガルバリウム・トタン・アルミ・ステンレスの製品(屋根は除く)・木製品
<塗料タイプ>
- 架橋反応型水性シリコンアクリルエマルション樹脂塗料
<サビがある場合の下処理>
- ボロボロと取れるようなサビは、皮スキ・ワイヤーブラシで落とします
- 細かい部分はスチールウール・サンドペーパーでサビを落とし、サビ・ゴミ・油分などをペイントうすめ液でよく拭き取り乾かします
アサヒペン水性高耐久鉄部用はこちら。
サビが発生しやすい素材

外壁や鉄骨階段、手すり、雨樋、ベランダなどには鉄が使われることが多く、サビが発生しやすい場所です。鉄以外の外壁や屋根でも、もらいサビによりサビが発生する可能性があります。
自転車やスコップなどの鉄製品が、壁に触れることでサビをもらってしまうのが、もらいサビです。もらいサビで発生したサビは威力が強く、サビの浸食や内部の劣化が早いので注意が必要です。
こちらの記事でも、鉄の部分で起こりやすいサビ!を解説しているのでご覧ください。
金属系サイディング

外壁の種類は大きく3つに分類されます。
- モルタル
- 窯業系サイディング
- 金属サイディング
このなかでサビの発生が懸念されるのが、金属系サイディングです。金属系サイディングは、名前のとおり金属からできているので、水に触れるとサビが発生しやすくなります。
水の浸入のほかにも、塗膜が剥げ表面に傷がついている外壁や屋根は、サビの進行を早め、外壁の寿命を縮めるので要注意。
ガルバリウム鋼板でもサビは発生する

ガルバリウム鋼板は、高性能でメンテナンス不要のものが多いので、外壁に使用する方が増えています。アルミニウム・亜鉛・シリコンで配合された合金で、耐久性が高く、犠牲防食機能も兼ね備えたサビができにくい外壁材のひとつです。
ガルバリウム鋼板の耐用年数は、25年〜30年といわれています。メンテナンス不要と言われることもありますが、きちんとメンテナンスしないとサビが発生しやすく、耐用年数も短くなってしまいます。
特に、もらいサビ・赤サビ・白サビには注意が必要ですが、定期的なメンテナンスを心がけていれば、長くキレイな状態を保てるのでご安心ください。
こちらの記事でも、鉄の部分で起こりやすいサビ!を解説しているのでご覧ください。
外壁のサビを放置するとどうなるのか

外壁のサビは、発生原因をつきとめて適切な補修をしない限り、時間の経過とともに症状が広がってしまいます。ある程度サビが進行すると、お家の寿命を大きく縮めてしまうことにもなりかねません。
ここからは、外壁のサビを放置した場合のリスクをご紹介します。
- 外壁の張り替えが必要になる可能性がある
- 金属製の外壁の場合には穴が開いてしまうことも
- 柱や梁などの構造躯体にまで大きなダメージが及ぶ
このように、補修するにも大規模な工事になり、外壁をそっくり張り替えることになり、費用も膨大にかかってしまいます。サビが進行している場合には、早めに信頼できる業者に相談することを心がけましょう。
関連記事:サビこそやっつけよう!~金属製サイディング、鉄の柱など~
サビてしまった外壁や屋根の塗装工程

サビてしまった外壁や屋根は、劣化が内部でも進んでいる可能性があります。表に出ているサビの放置は、お家や街並みの景観を損なうだけでなく、外壁の寿命を縮める要因です。
サビの補修をした直後は、どのような作業をおこなっても、表面上はきれいになるので納得の仕上がりになると思います。
しかし、サビは時間の経過とともにまた進行するので、表面的な補修をしただけでは意味がありません。
サビが完全に除去されていない状態で、新たな塗料を塗って、表面を塗膜でふさいでしまうと、外からは見えない部分でサビが進行してしまいます。外壁の状態に応じて、ケレンや張替えなどの補修が必要なので、信頼できる専門業者に依頼するのがいいでしょう。
ここからは、業者がおこなう外壁の塗装工程を解説します。
高圧洗浄

まずは、発生したサビをキレイに洗い流すことからスタートです。
雨水や紫外線の影響を受けた外壁は、サビやホコリ、目に見えない細かい汚れもあるため、パワーのある高圧洗浄機で汚れを落とし乾燥させます。
汚れが残っている外壁に塗装すると、劣化が早く、せっかくの塗料が剥がれ落ちる原因に。まずは、外壁の汚れを洗い流し、塗料を塗るための下地を丁寧に整えることから始めます。
ケレン(研磨)

ケレン作業とは、外壁の異物を取り除く作業のことで、素地調整ともよばれます。高圧洗浄機である程度キレイになった下地を、さらに整えることで、塗料のもちがよい美しい外壁に仕上がります。
汚れやサビが軽いものであれば、ケレンは大がかりな工事ではないでしょう。
しかし、サビが大きくコブのように膨れあがって、外壁材の深部まで進行していると、電動工具などを使って除去しなければいけません。高品質でグレードの高い塗料を使用しても、外壁材の下地が整ってなけければ、耐久性を落とす原因になります。
ご自身でケレン作業が難しい場合は、経験豊富な職人がそろうミヤケンにお任せください。
サビ止め塗装(下塗り)

外壁の下地を整え、塗料が密着しやすい状態になったら、まずはサビ止め塗料から塗布していきます。
外壁や屋根に使用されるサビ止め塗料は、油性タイプとエポキシ樹脂タイプの2種類が主流です。このほかにも、ウレタン樹脂タイプ・エッチングプライマーがありますが、外壁材やサビの状況によって使い分けます。
下地材にも色がついているので、このあとに塗る塗料に影響しないように、色選びも重要なポイント。サビや腐食を防ぐ重要な工程なので、外壁や屋根のほか、雨樋や金属部分にも丁寧に塗布して下地を仕上げます。
上塗り

塗装は、下塗り・中塗り・上塗りの3段階あり、上塗りは塗装の最後の仕上げの工程です。どの段階にもそれぞれの役割があるので、丁寧に作業しなくてはいけません。
上塗りの役割としては、中塗りで生じた色むらや気泡を覆い隠し、雨風から外壁を守ることが挙げられます。
さらに、見た目を決定づける作業でもあり、外壁のツヤがキレイに仕上がるかどうかは上塗りで決まると言われています。耐熱性やカビに強い塗料や、特別な性能を保つ塗料もあるので、状況に応じてお選びください。
こちらの記事では、ミヤケンのサビ塗装を詳しく解説しているので、ご確認ください。
関連記事:サビてしまった鉄製の折半(せっぱん)屋根の塗装工程のご紹介
外壁のサビを予防する方法

お家の外壁をキレイな状態をキープするために、どのようなことができるのか、サビを予防する方法をご紹介します。
もらいサビ予防のためにはまずは、建物の近くにサビが移ってしまう恐れがあるものを置かないことです。自転車や脚立、スコップなどを長時間立てかけていると、外壁にサビがうつってしまいます。まずは、建物の近くを整理して、もらいサビを予防しましょう。
新築時に、防腐剤を含んだ塗装をしていれば、防水機能でサビは発生しにくい状態ですが、効果が永久に続くわけではありません。時間の経過とともに劣化し、外壁は水が溜まりやすい状態になります。
ひび割れや塗膜の劣化でできたサビは、初めは壁内部で発生し、少しずつ外壁に浮きあがって目に見える状態になります。表面のサビを取り除いても、内部のサビは進行を続けるので、外壁に穴が開いてしまう可能性も。
このような事態にならないためにも、外壁や屋根は、定期的にメンテナンスや点検をおこないましょう。外壁のメンテナンスは10年程度を目安に、目視での確認と併せて、建物内部の確認は専門業者への依頼をおすすめします。
早めに異変に対処できれば、補修にも費用がかからず、すぐにキレイな状態を取り戻すことができるでしょう。お家の状態を正しく把握するためにも、定期的なメンテナンスを心がけてください。
業界唯一の定期点検

今ではどの業者でも、10年ほどのアフターサービスが付帯しているプランは珍しくありません。ミヤケンでは、業界唯一12年のアフターフォローで、工事後も安心していただけるサービスを提供しています。
塗装工事後は専任スタッフが、1年・3年・5年・7年・10年・12年後にお家の点検に伺い、補修箇所があれば、工事の段取りを立て、お客さまにご連絡します。
末長く安心して暮らせるように、外壁のメンテナンスもミヤケンにお任せください。
詳しい内容は業界唯一!最長12年間無料! 調査スタッフによる訪問点検をご覧ください。
まとめ

今回は、外壁のサビの発生原因や対処方法を詳しく解説しました。表面に出てきているサビは、外壁内部にも腐食が進行しているかもしれないので要注意です。
お家がどのような状態なのか見極めるには、定期的なメンテナンスや点検が必要になります。これからも長くキレイなお家に住むためにも、サビなど気になる症状があれば、ミヤケンにご連絡ください。
ミヤケンでは無料で建物診断をおこない、メンテナンスのアドバイスやおすすめの塗装をご紹介できます。お電話やメール・Webからも受付していますので、お気軽にお問合せください。
▼WEB申し込みは24時間受付中!(深夜のお問い合わせもOK!)▼
▼お電話でのお見積もり依頼をご希望の方はコチラ▼
フリーダイヤル【0120-286-440】
前橋店【027-289-3838】
高崎店【027-384-3939】
太田店【0276-57-6969】
※受付時間9:00~18:00
▼塗装について直接お店でご相談をしたい方はコチラ▼
【ご来店予約】
※来店予約は24時間受付しております。
営業時間は9:00~18:00です。